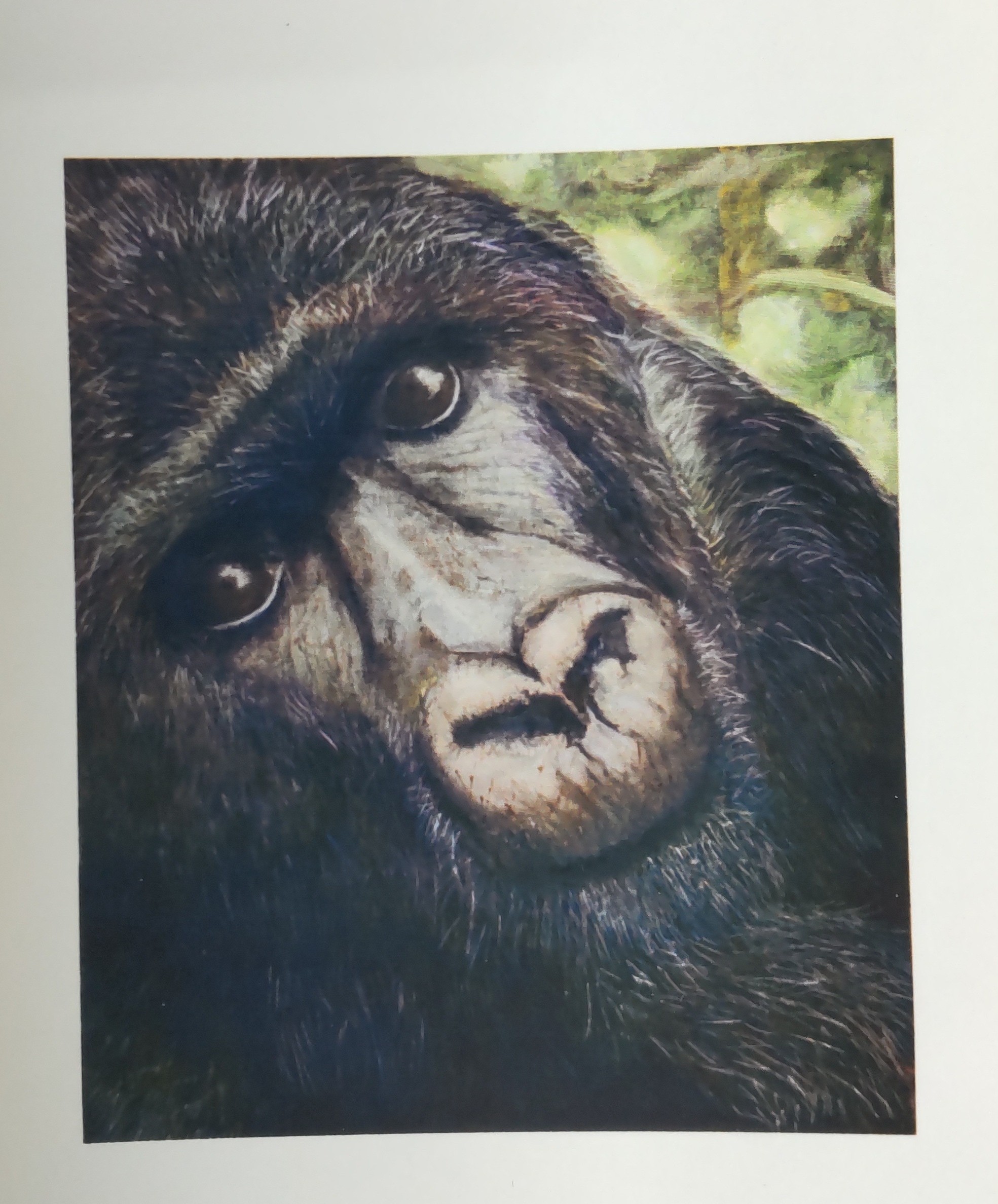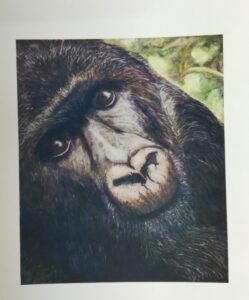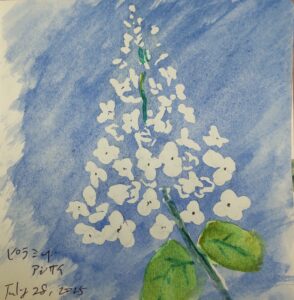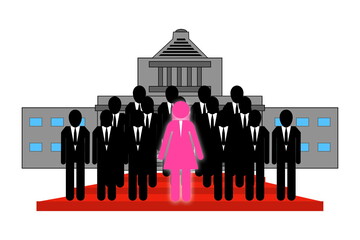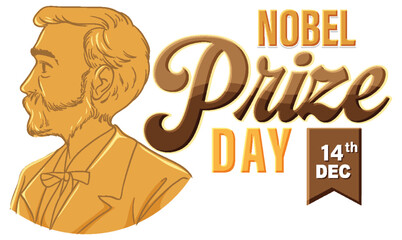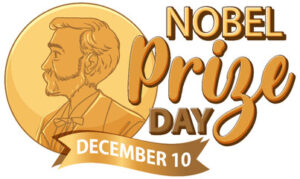ワールドシリーズの相手がトロント・ブルージェイズに決まりました。思い起こせば8年前2017年5月に仕事でトロントの小児医療センターを見学し、余暇を利用して、ナイアガラ・フォールズを見に1時間半ほど車を飛ばして行ってきました。その時ラジオで今日「トロント・ブルージェイズ」と「テキサス・レンジャース」の試合があり、レンジャースのダルビッシュ有投手(2017年7月にドジャースにトレードされました)が投げると聞き、急いで戻って当日券を買おうと列に並びましたが、少し前でソールドアウト、仕方がないので近くのスポーツバーのテレビで観戦していたことを思い出しました。次の仕事でクリーブランドへ行って、仕事を終えた後、折角なんでクリーブランド・インディアンスの試合を見に行きました。その当時は、弱かったですが、クリーブランド・ガーディアンスに命名変更してからは、2024年2025年と地区優勝していますが、ポストシーズン1回戦で敗退しています。この度ドジャースの対戦相手がブルージェイズに決まって8年前のトロント訪問を思い出しました。ホンマに懐かしいなー。
土曜日は見事にブルージェイズに4対11と打ち負けました。ドジャースの唯一の見せ場は、11点取られた後の大谷のツーランホームランだけ、日曜日は、逆でドジャースが5対1で勝ちました。山本由伸がポストシーズン連続の完投勝ちは、24年ぶりの快挙だそうです。火曜日からロサンゼルスの本拠地ドジャースタジアムでの3連戦、楽しみです。
懐かしい 8年前が 蘇る
ウエッジを クリーブランドで 買ったんや
よく見ると 「Made・In・China」と 書いてある
トロント・ブルージェイズ一口メモ:トロントの本拠地のスタジアムは、「ロジャーズ・センター」といいますが、以前は「スカイドーム」と命名され、世界初の可動式屋根付き多目的スタジアムだったそうです。2004年にカナダの大手通信企業「ロジャーズ・コミュニケーションズ」に買収されて、「ロジャーズ・センター」になりました。
トロント旧市庁舎


ナイアガラフォールズ


ブルージェイズの本拠地(ロジャーズセンター)


クリーブランドインディアンズの本拠地球場