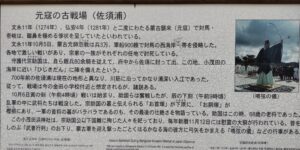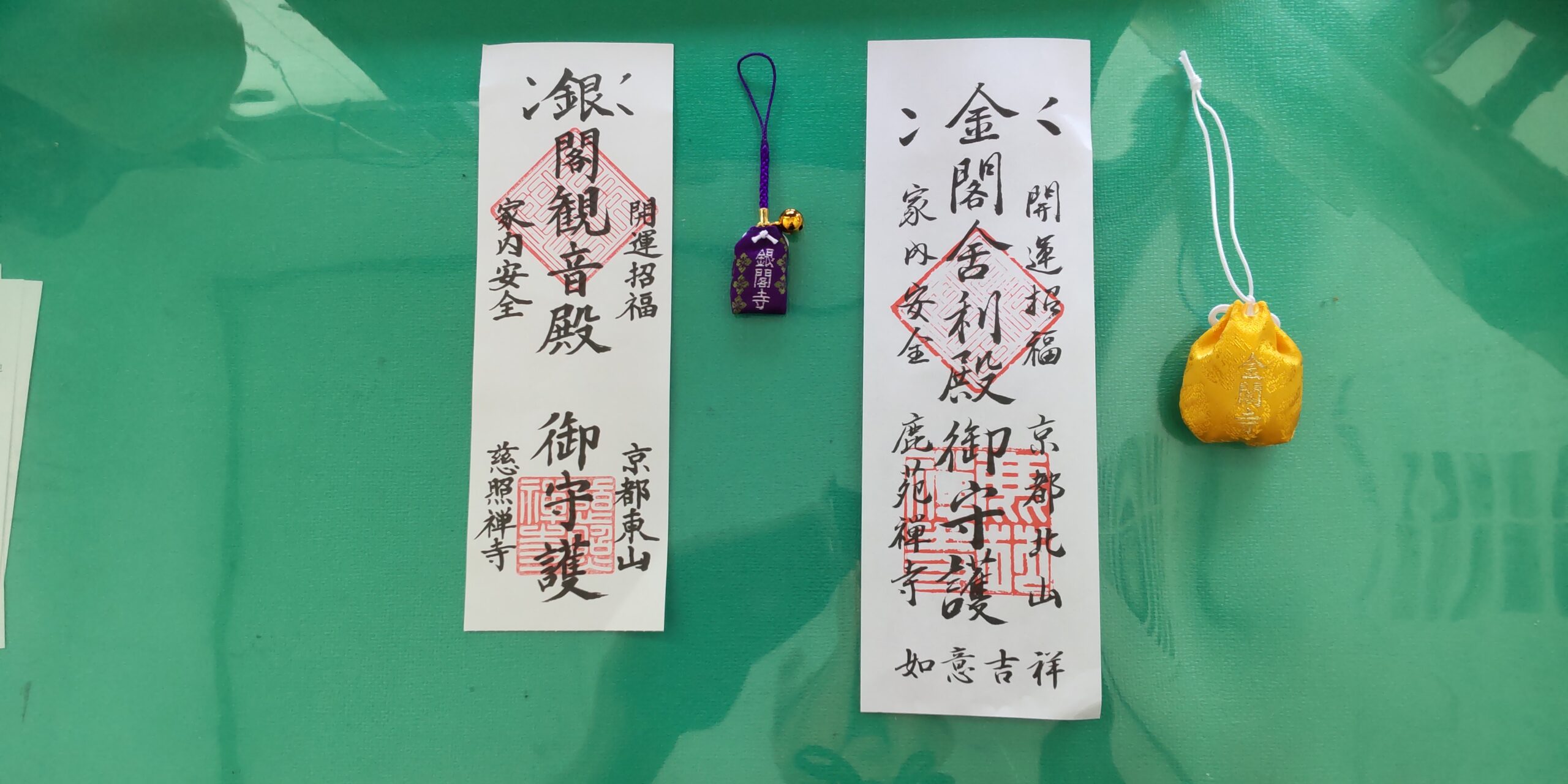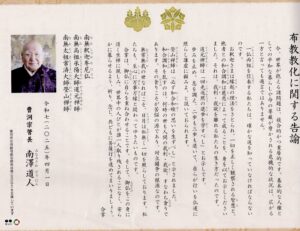猪名川町は今回、参議院兵庫県選挙区選出議員選挙、猪名川町長選挙、猪名川町議会議員補欠選挙の三つの選挙がありました。参議院選挙は13名立候補され、3名当選、兵庫県は今、公益通報の問題や斎藤元彦知事の再選に関連した二馬力選挙など県政は大いに揺れています。その関係か多くの方が立候補され、多様なバックグラウンドを持つ候補者が立候補され、全国の注目を集めています。合わせて、猪名川町も道の駅中止による購入した跡地の問題で裁判沙汰となっており、兵庫県と同様、今回の町長選挙の行方を我々町民も見守っております。町長選挙には、現職の町長を含め5名立候補され、その内2名の現職の町会議員の方が辞職、立候補されましたので、補欠選挙に6名立候補されて2名当選、以下の通りの結果となりました。
参議院兵庫選挙区当選者:一位泉 房穂/822,407票(無所属)・二位高橋 光男/339,822票(公明)・三位加田 裕之/285,451票(自民)・次点吉平 敏孝/275,301票(維新)
町長当選者:岡本 信司5,079票(現職再選)・次点高岡 美津子4,440票
町会議員補欠選挙当選者:一位小林 おきと4,963票・二位車 ひろし4,131票・次点こひがし 明子3,819票
参議院選挙の投票率は58.51%で前回よりも6.46ポイントも増えました。それだけ国民の関心も高く、与党の過半数割れという結果となりました。今後の政局の運営も難しくなり、石破首相の責任も問われており、アメリカのトランプ大統領による関税の引き上げによる経済活動の停滞と合わせて、日本の先行きはますます混迷を深めるようになり、大変不安ですね。私の住んでいる猪名川町も町長は再選され、新しい町会議員2名が選ばれました。猪名川町の投票率も65.6%と高く、前回よりも11.17ポイントも増えており、関心の高さを示しています。道の駅の跡地の活用や税収の減少、空き家対策、北部地区の過疎化、休耕農地の増加など多くの問題を抱えています。国も町も今回選ばれた方々に頑張っていただいて、政治も経済も少しでも上向きになるように期待してまっせ。